知育ってなに?
知育玩具と普通のおもちゃの違いは?
良く耳にする「知育玩具」って、いったいどんなおもちゃなんでしょうか?
学習系おもちゃ? 何らかの知識を得るためのおもちゃ?
実際には、「知育玩具」と「普通のおもちゃ」を意識して買い分けている方は、そう多くないかもしれません。
そこで今回は、知育玩具の目的やメリット・デメリット、普通のおもちゃとの違い、そして年齢別におすすめの知育玩具をご紹介していきます。
【この記事を読むとわかること】
- 知育玩具の目的と効果
- 知育玩具の歴史と種類
- 知育玩具の注意点
- 一般的なおもちゃ、モンテッソーリ教具、教材との違い
- 年齢ごとのおすすめ知育玩具
知育玩具ってなに? どんな目的・効果のおもちゃ?
知育玩具とは、「子供の知能や知力を高めるように設計されたおもちゃ」のこと。
単純に学習能力を身に付けるばかりではなく、遊びながら思考力や集中力、創造力、問題解決能力、社会性などを育むことを狙いとしています。
 筆者
筆者つまり、「人間としてたくましく生きる力」を育成するためのおもちゃ。
また、それらの知育の効果を高めるためには、「知育=頭」「徳育=心」「体育=身体」の3つを連動させ、バランスよく育てることが肝心とも言われています。
そのため、知育玩具は知力ばかりでなく、遊びながら考えたり、表現したりすることを通して、手先の器用さ・視覚・聴覚・身体能力などを同時に伸ばせるよう設計されたものが多くあります。
知育玩具の歴史
知育玩具が誕生したのは、1950年代。その頃開発された有名なおもちゃが「レゴブロック」です。
レゴブームに伴って、すでにあった積み木が、知育玩具として見直されたのもこの頃です。



今でもたくさんのファンがいるレゴ。
70年以上の歴史があるんだね!
1970年代に入ると、日本では教育ブームに突入し、本格的に知育玩具が普及していきました。
その頃の知育玩具は「子どもを勉強させることを目的とした教材」のようなものがほとんどで、あまり人気のない玩具もあったようです。
現代では、デジタル技術の進歩により、電子的な知育玩具も広く利用されるようになりました。



タブレット型の知育アプリやゲームなどが人気ですよね。
知育玩具の歴史は時代とともに進化してきましたが、子供たちの学びと発達を促進する役割は変わることなく、「今も昔も重要な教育ツール」として活用されています。
知育玩具の種類
現代の知育玩具には本当に様々な種類がありますが、例えば次のようなものがあります。
・形状や色を認識するためのパズルやブロック
・文字・数字・アルファベットを学ぶためのカードや積み木
・科学的な原理や概念を理解するための電子おもちゃや実験キット
・論理的思考や戦略性を学ぶためのゲームやパズル
・音楽や美術に触れるための楽器やお絵描きツール
・生活習慣やマナーを身に付ける時計や図鑑
・社会性を身に付けるおままごとやごっこ遊び
実際には、上記以外にも知育玩具は多くの種類があります。
しかし、そのすべてが子供たちが自分で考え、触れ、実際に操作することで学びを深めることができるように作られているのが特徴です。
知育玩具のメリット・デメリット
知育玩具で効果的に遊ぶには、知育玩具のメリット・デメリットを知っておく必要があります。
メリットばかりありそうな知育玩具ですが、実はデメリットも存在するのでチェックしていきましょう。
| メリット | デメリット |
|---|---|
| 楽しみながら知識を身に付けられる 論理的思考や問題解決力が身に付く 就学前の学習準備ができる 手先が器用になる 自己肯定感が上がる | 親の指導や手助けが必要 発達段階に合わせる必要がある 一部の玩具は高価 |
知育玩具の最大のメリットは、知識や物事を深く考える力、問題を解決する力などが、遊びながら身に付くことです。
幼児のうちから活用すれば、小学校で必要となる学習の準備や生活習慣・社会的マナーを身に付けることもできます。
また、 知育玩具は達成感や成功体験を得るものが多いので、子供たちの自己肯定感や自信を高めるメリットもあります。
一方で、デメリットとして知っておきたいのは、知育玩具で効果的に遊ぶためには、親のサポートや指導が必要になるケースがあること。
知育玩具ははじめは遊び方がわからなかったり、遊び方にコツがいるおもちゃがあるため、親がそれぞれの知育玩具の目的や効果をあらかじめ知っておく必要があります。



知育玩具は、いつでも子どもの食いつきがいいわけじゃない…
また、知育玩具に書かれている対象年齢以上に、子どもの興味や発達段階に合わせたおもちゃを選ぶことも、知育玩具においては重要になってきます。
一部の知育玩具は高額なので、おもちゃレンタル(サブスク)などを上手に利用して費用を抑えることを検討してもいいかもしれません。
これらのメリットとデメリットを考慮しながら、まずは適切な知育玩具を選ぶことが重要です。
また、知育玩具は他の教育方法や経験と組み合わせて利用することで、総合的な学びが高まるということも知っておきましょう!
知育玩具とおもちゃの違い
では、知育玩具と一般的なおもちゃにはどんな違いがあるのでしょうか?
知育玩具:知識や知能の発達を高めることを目的
おもちゃ:娯楽や身体活動、社会的な交流を目的
簡単に説明すると、以上のように目的が違うおもちゃをいうことになります。
知育玩具は、教育の一環として子供たちの成長や学びをサポートする役割を果たします。
一方で、おもちゃは主に娯楽や遊びの要素を提供し、子供たちが一緒に遊ぶことにも焦点が当てられています。



ただし、知育玩具とおもちゃの境界は明確ではなく、ときにひとつが両方の要素を持つこともあります。
また、子供たちにとっては、楽しむことと学ぶことは密接に関連していて、知育玩具を通じた学びが楽しみにつながり、おもちゃを通じた楽しさが学びの経験となる場合も多いです。
知育玩具とモンテッソーリおもちゃとの違い
今話題の「モンテッソーリ教育」に基づいたおもちゃ(教具)も、教育的な観点から設計されている点では共通しています。



藤井聡太棋士が遊んだ「キュブロ」や、円柱さしが有名だね!
モンテッソーリおもちゃは、イタリアの教育者・医師であるマリア・モンテッソーリの教育理論に基づいて開発されたおもちゃ(教具)のこと。
モンテッソーリの教育理論は、子どもは元々自己教育力を持っており、その力を伸ばす環境を大人が用意することが大切と言われています。



つまりモンテ教具は、子供が自ら学ぶための環境づくりの一環なんだね
モンテッソーリおもちゃは、子供たちが自主的に手に取り遊ぶことで学びを深めることを重視し、子供の情緒・運動の発達、自己認識、集中力、そして日常生活のスキルを促進するために設計されています。
一方、知育玩具は、もっと幅広い教育の観点から設計されています。
知育玩具には、形や色の認識、数学・言語能力、科学的な理解、創造力など、広範囲なスキルや能力を高めるおもちゃも含まれます。



そう、知育玩具は学習的な要素も強い!
どちらも子供たちの学びを促進することを目的としていますが、教育理論やアプローチの違いにより、それぞれが異なった特徴を持っています。
教材と知育玩具の違い
教材と知育玩具は、どちらも教育の観点から使用されるものですが、使用されるシーンに違いがあります。
教材は、特定の教育目標やカリキュラムに基づいて設計された教育資材のことで、通常、学校などの教育機関で使用され、教師や教育者が教育プロセスをサポートするために使用されます。
例えば、教科書、ワークシート、プリント教材、教育ソフトウェアなどが教材の一部ですね。



今では、通信教材などもあります
一方、知育玩具は子供たちの知識や知能の発達を促進するために、家庭や保育園、幼稚園など、子供たちの日常の遊びや学びの環境で利用されることが一般的です。
ただし、教材と知育玩具の違いも、明確に定義されるものではありません。
教材と知育玩具は、お互いに補う形で、子供たちの学びと発達をサポートしていくことが理想の教育環境と言えますよ。
【年齢別】知育玩具のおすすめ
知育玩具は、一般的なおもちゃと同様対象年齢が設けられていますが、「発達に応じて選ぶ」ことが最大のポイント。
必ずしも、年齢に応じたおもちゃで遊ぶ必要はなく、知育玩具は子供の興味や関心、親が伸ばしてあげたい能力にお応じて選ぶことが重要です。
ここからは、年齢ごとにおすすめの知育玩具をご紹介していきます。
| 年齢 | おすすめの知育玩具 | 伸ばしたい力 |
| ~3ヶ月(ねんね期) | メリー/ベビージム 木製ラトル/ | 視覚・聴覚 |
| ~7ヶ月(お座り期) | ルーピング/布積み木/ おきあがり小法師/ ラッパ/リモコンおもちゃ | 追視 手全体の運動能力(つかむ・投げる) |
| ~11ヶ月(ハイハイ期) | 積み木/ニューブロック 多目的キューブトイ 手押し車/プルトイ | 指先や眼の運動能力 色の認識・図形感覚 創造力 |
| 1歳 | レゴデュプロ/ 型はめパズル/玉転がし こどもずかん/図鑑カード ジャングルジム/滑り台 | 図形感覚・立体の感覚 指先や眼の運動能力 語彙の増加 創造力・歩きの安定 |
| 2歳 | ままごと/ひらがな積み木 タングラム/型はめパズル 数字パズル/ 太鼓/ミュージックマット ストライダー/キッズテント | 数や図形の概念 感受性・音感・語彙力 社会性・創造力 全身運動 |
| 3歳 | マグネットブロック/ スロープおもちゃ 玉そろばん/粘土 ジグソーパズル/立体パズル ストライダー/トランポリン | 社会性・想像力・創造力・ 空間認識力 文字の読み・語彙力 図形感覚・立体感覚 全身運動 |
| 4歳 | プログラミングおもちゃ ロードパズル/時計 ひらがなタブレット/ レゴ/アクアビーズ/ ボードゲーム/カードゲーム | 空間認識力・語彙力 論理的思考・表現力 生活習慣・マナー コミュニケーション力 文字の書き |
| 5歳 | 算数おもちゃ/学習タブレット プログラミングおもちゃ 学習顕微鏡/時計 レゴ/モザイクパズル ボードゲーム/カードゲーム | 表現力・語彙力 論理的思考・観察力 コミュニケーション力 問題解決力・戦力性 生活習慣・マナー |
| 6歳 | 算数おもちゃ/学習タブレット プログラミングおもちゃ 学習顕微鏡 ボードゲーム/カードゲーム 科学実験キット 組み立てキット | 表現力・語彙力 論理的思考・観察力 コミュニケーション力 問題解決力・戦力性 生活習慣・マナー |
年齢に合わせた選び方も大切ですが、子供の成長や興味に合わせて選ぶことが最も大切です。
子供たちが自由に遊び、自己表現や創造力を発揮できるような環境づくりを心掛けるようにしましょう。
子供の発達に合わせた知育玩具の選び方
ここまで、子供に合った知育玩具を選ぶには、年齢以上に子供の興味や発達段階を良く知ることが大切ということをお話してきました。
しかし、子供の発達に合った知育玩具を選ぶのは、毎日を一緒に過ごす親でも難しいことも。
【口コミ調査】知育玩具選びの悩み
日々のおもちゃ選びで以下のような悩みを抱えるパパママが多くいます。
| 赤ちゃん~歩きはじめの頃 | どれが知育玩具かわからない 目に見えた効果が出にくい |
| 1歳~2歳 | 知育玩具に飽きやすい 集中して遊んでくれない 対象年齢のおもちゃが少ない |
| 3歳~ | 似たような知育玩具が多くベストがわからない 子供の能力に合う知育玩具がわからない 知育玩具が高い |
ちなみに、筆者は以上のような悩みを解決するのに、「おもちゃのサブスク」を選んでいます。
おもちゃのサブスクとは、月額料金を支払って、6点ほどのおもちゃを交換し放題で遊べるサービス。
子供の発達の専門家や保育士などが、1人1人の個性や発達段階をヒアリングした上で、知育おもちゃを選んでくれるため、子供の五感の発達やお勉強に向けての準備をおもちゃでサポートできます。



おもちゃを持たないので、部屋がすっきり片付くのもいいですよ!
▼少し気になる方は、お試しできるおもちゃのサブスクをチェックしてみてください。
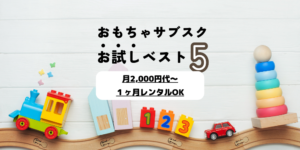
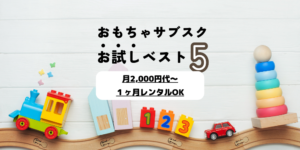
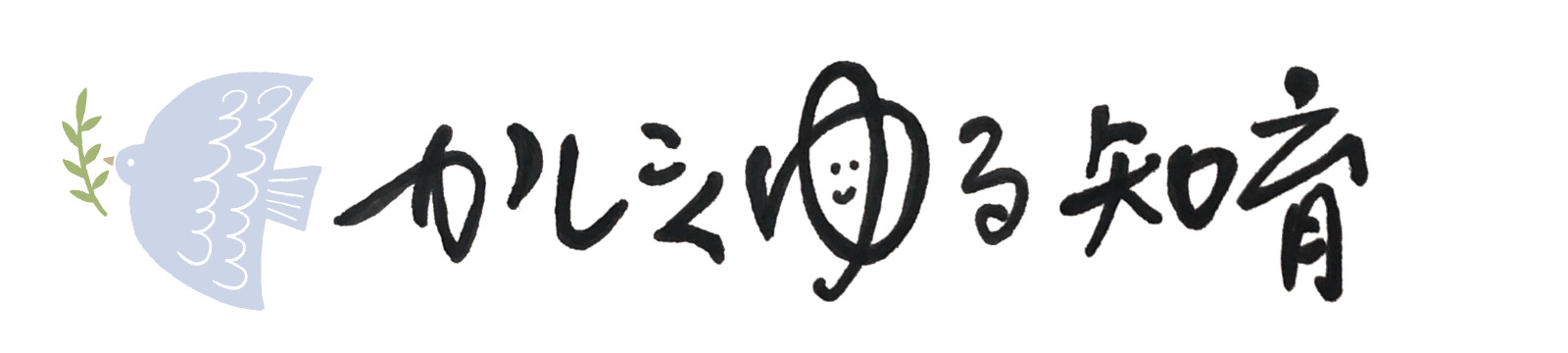
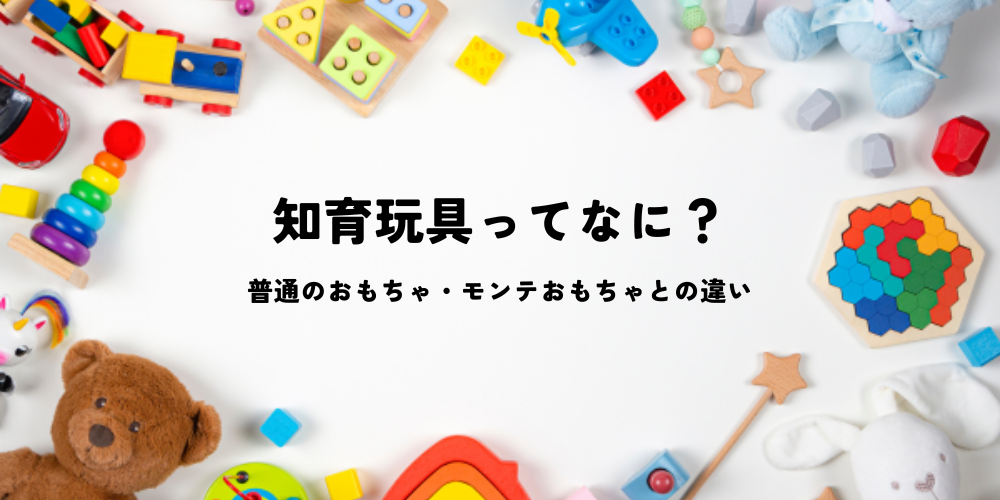
コメント